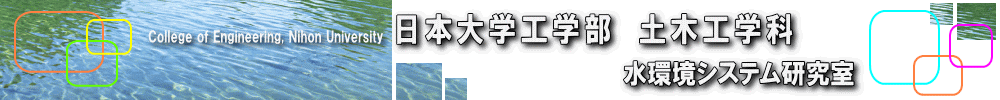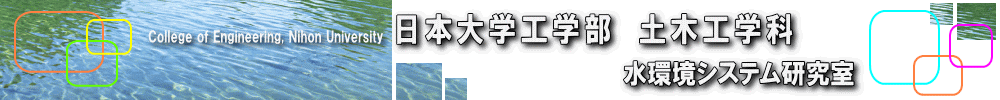.
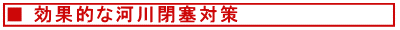 |
■ 研究概要
中小河川の河口状況は多様であり、また、自己流量が少なく外力の影響を受けやすいため河口閉塞
になりやすい傾向にあります。
河口閉塞により河川内水位が上昇し、周辺地域に浸水被害を及ぼした例は少なくありませんが、
その一方で中小河川は大河川に比べてデータ整備遅れており、効果的な河川閉塞対策を確立する
までには至っていません。
本研究では、中小河川の河口変動状況を長期的及び短期的に追跡し、河口閉塞のメカニズムの解明
と、より効果的な対策について検討します。
|
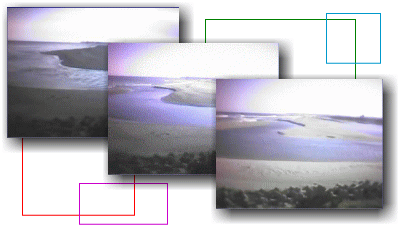 |
■ 1.中小河川の河口特性
岩手県から茨城県に位置する計116河川の調査によると、海岸に対して南側に位置する河川は左岸
堆積が、北側に位置する河川は右岸堆積が多くみられました。
また、河口処理については、海岸の端部に位置する河川ほど高い効果が得られています。
さらに、ここでは「河口変動指標」として、比較的入手しやすい資料によって河口変動の頻度を推定
する手法を提案しています。
■ 2.夏井・四倉海岸の海浜過程性
夏井・四倉海岸において、海岸砂の粒径調査及び河口の砂嘴状況調査を実施しました。
粒径の時系列変化から、海岸の北端では北向き、南端では南向きに、沿岸漂砂の卓越方向が変化
している様子が伺えます。
また、海岸内の砂の平均粒径分布から、沿岸漂砂の主な漂砂源は夏井川水系であることがわかり
ました。
一方、新舞子ビーチの突提建設による影響を追跡すると、突堤建設後の5年間程度は河口特性が
不安定となり、その後、回復する様子が見られました。
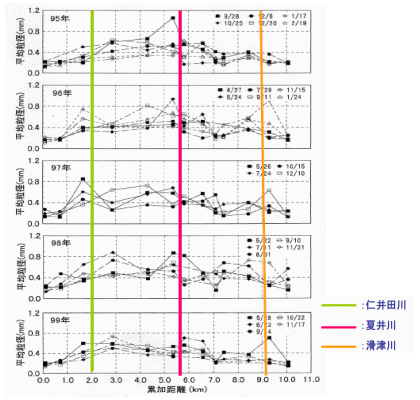
|
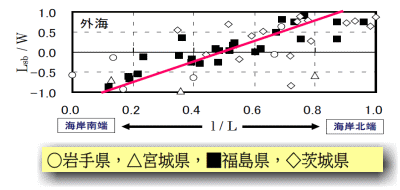
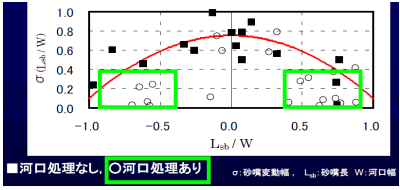
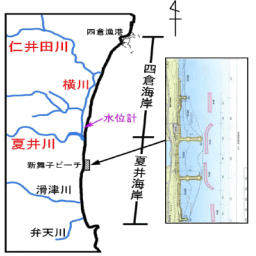
|
■ 3.夏井川の河口閉塞
夏井・四倉海岸の主な漂砂源となっている夏井川について、水位計、監視カメラ、GPSを使用した
河口調査を実施しました。
調査結果を砂村・堀川のCパラメータを用いて分析すると、本海岸における前浜への堆積は、波高0.7
mから0.8m、波形勾配0.008程度であり、侵食は波高1.6m以上、波形勾配0.014以上の波に
よってもたらされていることがわかりました。
2006年9月から11月にかけて長期的な河口閉塞が生じた原因は、高潮位による堆積型の海象条件
が継続したためと考えられます。
≪砂村・堀川のCパラメータ≫
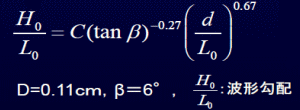
|
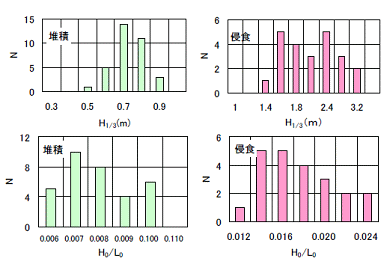 |
■ 4.効果的な河口処理対策の検討
(1)開削工について
夏井川では河口閉塞時の対策として人工開削を行っています。実施時期は不定期であり、河口内
水位が高く、周辺地域への浸水の危険性があるときに、県の委託業者の判断で行われています。
福島県の記録によれば1999年から2002年までの間に60回の開削工事が実施されましたが、
開削が行われても河口内水位が低下しない場合や、開削後数日で閉塞傾向となる場合が見られ
ました。
これらの課題を解消するため、現地観測や水理模型実験により開削工が効果的に作用する条件を
整理し、開削工の実施条件の定量化を図ります。
(2)導流壁について
河口閉塞を未然に防止する対策として、導流壁を設置して、河川流の掃流力の増大を図るものが
あります。
水理模型実験を実施した結果、導流壁は、その設置位置により得られる効果に差があることが分か
りました。効果的な導流壁の設置条件について、砂丘堤防の高さや位置との相対関係に着目し研究
を進めております。
|
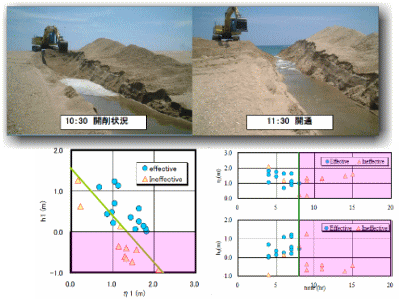
セミナー資料はこちら >>>>
|
.
|